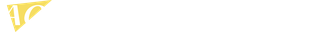HIV研究の功労者 杉浦 亙先生インタビューを執筆しました Vol.2
国立国際医療研究センター 臨床研究センター長の杉浦亙先生に、HIV/エイズ研究の現状と未来について伺いました。疫学データを活用した感染経路の解明が、感染拡大防止のための科学的アプローチ、研究費の課題などが語られました。そして多忙な中でも音楽やダイビングを楽しみ、心の豊かさを大切にする生活姿勢が印象的でした。(2025年4月21日インタビュー 計2回連載の2回目)

―現在は臨床現場には携わっておられないとのことですが、患者さんと接する機会はありますか?
自分自身が患者を直接診ることはありません。名古屋医療センターに勤めていた時はベッドサイドに近いこともあり、相談役のような立場で関わることはありました。2000年ごろまでは内科医としても多少診療をする機会がありましたが、それ以降は臨床からは離れています。現在も患者さんと全く接していないわけではなく、学会などでは感染者の方とお話することもありますし、研究協力者の方々とも対話することはあります。ただ、医師という立場で診療の場で接するということはないです。
―世間からの反応は先生のところに届いていますか?
「世間一般」の方々からの反応というものが私のところに直接届くことはほとんどありません。日本は先進国の中ではHIV/エイズ患者数が少ないという現状です。年間の新規感染者は1000人程度で、「世間一般」の方の関心が高まりにくいのではないかと思います。結果として、多くの方にとってHIVは「身近な問題」として認識されていないため、自然と反応も少ないのではないかと考えています。
―コミュニティの中での反応はいかがでしょうか?
感染者や関係者が集う場においては、状況は少し異なります。私が行ってきた調査研究について、初期の頃は警戒感もあったと聞いています。しかし班員の先生方が関係者の方々としっかりコミュニケーションを取り、情報共有を行いながら進めてきた結果、現在ではご理解いただき調査にご協力していただけております。
―調査開始当初にあった反発について、もう少し教えてください。
調査を始めた2003年ごろには、特に遺伝子解析を用いた研究に対して「犯人探しではないか」という誤解が一部にあったようです。我々は系統樹を作成して、感染のつながりを科学的に分析していただけですが、stigmaのこともあり不安や警戒心が強かったのだと思います。
しかし、時間をかけて活動を続ける中で、私たちの研究の目的や姿勢が理解され、「これは責任追及ではなく、感染状況の理解と感染拡大防止のための科学的アプローチだ」と受け入れていただけたのではないかと思います。

―現在の研究環境はいかがでしょう?予算も必要だと思います。
HIVの研究費、特に基礎研究に関しては、非常に厳しい状況だと感じています。研究費は削減される一方で多くの研究資材や試薬は外国製で価格が高騰しています。かつてはいただいた研究費で研究機器を購入できる環境もありましたが、今はそうではありません。研究費の使い方や配分のあり方には、検討が必要だと感じています。
―日本における研究のあり方についてはどうお考えですか?
日本では予算のこともあり、研究者の層が米国に比べて薄いと感じています。研究は議論と競争を通じて切磋琢磨し、発展していくものです。人材育成も併せて投資をしていくことが必要だと思います。

―先生のプライベートな部分もお伺いしたいです。音楽に親しまれていると伺いました。
大学時代に先輩たちと一緒にオーケストラを設立しました。それから40数年、今では大きな団体になっていて、定期演奏会も45回を数え、OBの数も相当なものになっています。今も楽器の演奏は続けており医療従事者が中心のアマチュア管弦楽団に参加しています。医師だけでなく、薬剤師などたくさんの医療従事者が参加している楽団ですが、私は後ろの方で皆さんについていくという感じです(笑)。
団員のみなさんの音楽への思いは熱く、本当に忙しい中で活発に音楽活動に取り組んでいます。複数のオーケストラに所属している人や、プロ級の演奏家もいます。海外出張にも楽器を持っていき練習を欠かさない人もいます。自分で楽団を立ち上げて活動している方などさまざまです。
―最近はダイビングも始められたとか?
はい、2年ほど前から始めました。まだまだ初心者ですが、機材はフィンとマスクだけ持参して、その他はレンタルで楽しんでいます。
―お忙しい中を調整されて有意義な休日をすごされているのですね、平日のスケジュールはどうですか?
柴犬を飼っています。毎朝5時に起きて散歩に連れていくのが1日の始まりです。その後に仕事へ出かけるという生活です。早起きは時にはしんどいこともありますが、毎朝のお散歩は欠かせません。
平日は朝から愛犬とお散歩、休日はオーケストラとダイビングを楽しむ充実した毎日を送られている杉浦先生、ありがとうございました。
◆ 杉浦 亙(すぎうら・わたる)氏
平成4年 浜松医科大学大学院医学系研究科修了(医学博士)
平成4年 国立静岡病院内科医長(呼吸器内科)
平成6年 米国 NIH/NIAID 客員研究員
平成8年 国立感染症研究所エイズ研究センター、第 2 研究グループ長
平成20年 国立病院機構名古屋医療センター、臨床研究センター 部長
平成21年 名古屋大学大学院医学系研究科免疫不全統御学講座 客員教授
平成25年 第10回日本エイズ学会学術賞(シミック賞)を受賞
平成27年 グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部メディカルアフェアーズ部門上席部長
平成30年 ViiV Healthcare Asian- Pacific Medical Director
令和元年 ビオメリュー・ジャパン メディカルアフェアーズ本部長
令和 2年 国立国際医療研究センター 臨床研究センター長
令和4年 日本エイズ学会 理事長
【受賞】
平成25年 第10回日本エイズ学会学術賞(シミック賞)
編集後記
杉浦先生へのインタビューを通じて、HIV/エイズ研究の歩みと治療の進歩状況がよくわかりました。科学の進展には冷静な分析と共に、柔らかな感性も必要であると再認識させられます。多忙な日々の中でも心を豊かに過ごす時間を持つことの大切さを実感しました。音楽やダイビング、愛犬との生活に込められた杉浦先生のバランス感覚がとても印象的でした。