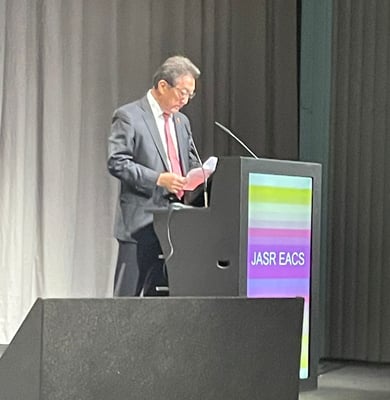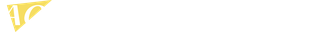HIV研究の功労者 杉浦 亙先生インタビューを執筆しました Vol.1
国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security: JIHS)に設置された臨床研究センターは、新薬や治療法を開発し、臨床に役立てる研究を行っている。HIV/エイズの薬剤耐性に対する監視体制を日本で整えられた臨床研究センター長を担う杉浦 亙先生に、HIV/エイズ治療のお話を伺った。(2025年4月21日インタビュー 計2回連載の1回目) ※HIV:Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス

ー杉浦先生は長年HIV/エイズの研究に携わっていらっしゃいますが、そのきっかけは何だったのでしょうか?
私はもともと呼吸器内科の医師で、大学を卒業してから臨床医として仕事をしていました。大学院時代に、HIV/エイズの研究をしている先生のもとでご指導いただく機会があり、その先生のご紹介で米国に留学することになったのが、HIV/エイズ研究に入るきっかけです。1994年の話です。幸運にもNIH/NIAIDの研究室に入ることができました。そこで師事したBernad Moss先生は、ワクチニア・ウイルスの研究で著名な方です。私はMoss先生が開発したワクチニア・ウイルスを用いたタンパク発現技術を応用したHIVのワクチン開発に取り組んでいました。
―当時のHIV/エイズの研究環境はどういう状況だったのでしょうか?
当時の状況を振り返ると、米国はHIV/エイズ研究に対して「全盛期」と言ってもいいほど、多くの研究資金が投じられていました。官民ともに精力的に基礎研究、ワクチンそして新薬開発を進めていた時代でした。
日本ではHIV/エイズに対する正確な情報がまだあまり広まっておらず、男性週刊誌が「アメリカでエイズという奇病が流行っている」といった報道をしていた時期でした。エイズの原因であるHIV自体は1983年に発見されていて、渡米当時は発見から10年ほど経っていました。治療薬は1987年に登場してはいたものの、その効果は限定的であり、現在標準治療とされている多剤併用療法は確立されていませんでした。
―HIVの感染メカニズムについても発展があったと聞きました
満屋裕明先生(現国立健康危機管理研究機構研究センター研究所 所長)が1987年に世界で初めてエイズ治療薬AZT(アジトチミジン)を開発され、初期のHIV/エイズ治療は始まっていた時代でしたが、薬剤耐性が大きな問題となっていました。
HIVが細胞に感染する際、二つのレセプターを使うのですが、一つは「CD4」と呼ばれるもので、これは当時から知られていましたが、もう一つの補助受容体、今でいう「ケモカインレセプター」についてはまだ発見されていなかったのです。私が所属していた研究室の研究者Edward Berger先生が、世界で初めてその補助レセプターCXCR4を見つけました。1996年のことです。そんな時代でしたね。

―HIV/エイズの治療薬は、ずいぶんと進歩しました。転機となったのはいつ頃だったのでしょうか?
1996年に新しい治療薬プロテアーゼ阻害剤が登場し、3種類の治療薬を組み合わせて多剤併用療法(HAART:Highly Active Antiretroviral Therapy)が始まり、それまでは病気の進行を抑える程度であった治療が、免疫機能を回復させることができるようになります。私がアメリカで研究していた1994年から1996年はまさにHAARTの開始という大きな変化が起こる時期でした。治療が進化する中で、次に求められたのが「薬剤耐性ウイルスのモニタリング」です。日本でも薬剤耐性研究を始めることになり、私がその研究を担当することとなり帰国することになりました。
―日本でのHIV研究の幕開けですね、先生はHIVの薬剤耐性に対する調査体制を日本で整えられました
HIVの薬剤耐性の遺伝子検査手法の確立とその提供、そして全国調査体制の構築は、私の日本における最も大きな仕事だったと思います。これを起点に、その後も継続してこの分野に取り組みました。1996年末に国立感染症研究所(当時は「国立予防衛生研究所」と呼ばれていました)に着任し、そこで一研究室のグループ長として12年間勤務しました。その後は名古屋医療センターへ移り、8年勤務ののちに後進にバトンを渡しました。
― その後製薬企業にご勤務されました
一般的な医師のキャリアとしては変わっています。企業はアカデミアとは文化が違うのでそれまでとは違う様々な勉強ができ、とても良い経験になりました。55歳の時です。そのまま定年まで企業で仕事をするつもりだったのですが、ご縁があり現在の国立健康危機管理研究機構(当時は国立国際医療研究センター)臨床研究センターに勤務することになりました。
―HIV/エイズの治療薬は、ずいぶんと進歩しましたね
「多剤併用療法(HAART)」は、本当に革新的でした。その次の転換は約10年後、2007年に訪れます。「インテグラーゼ阻害薬」の登場です。これは治療をさらに進化させる大きな一歩でした。その後、塩野義製薬が開発したインテグラーゼ阻害剤「ドルテグラビル」が登場し、今日のHIV/エイズ治療には欠かせない薬となっています。薬の進歩はその特性にもおよび、改良により体内での半減期が長くなり、合剤化が進んだことで1日1錠の服用 (STR: Single Tablet Regimen)で済むようになりました。
―それまでの治療薬というのは、どのような状況だったのでしょうか?
HAART開始当初は8時間おきに、しかも手のひらいっぱいの錠剤を服用する必要がありました。それにも関わらず、有効血中濃度の維持が難しく、少しでも服薬を忘れると薬剤耐性を獲得してしまう可能性と治療に失敗する危険がありました。私は米国留学からの帰国後に、その薬剤耐性に対応するための検査体制を整備する役割を担いました。その後新薬の登場とそれに伴うさまざまな改良、抗ウイルス効果の増強、薬物動態の改善そして薬剤耐性を選択しにくい構造の解明などが進められました。そして30年を経た今日、1日1錠での治療が可能となり、薬剤耐性による治療の失敗は非常に少なくなっています。おそらく失敗率は1%前後だと思います。驚くべき治療の進歩だと言えます。
―今後もHIV/エイズ治療は進んでいくのでしょうね、現在のHIV感染に関する研究や調査状況についても教えてください。
HIV/エイズについては、まだまだ新薬の開発研究が進んでいます。私は2003年から新規感染者のデータを集めて、日本におけるHIV薬剤耐性の動向そして国内で流行しているHIVの株を遺伝子解析を用いて追ってきました。HIV/エイズの感染動向を正確に把握することは、学問的にも公衆衛生的にも極めて重要です。この調査は、厚生労働省の研究班によって始められたもので、私は初代の班長を務めました。現在は3代目の先生がその役を引き継ぎ、20年以上にわたり調査は継続されています。この研究では日本で新たに診断されるHIV/エイズ患者の約4割を補足しており、これだけ長期かつ高い補足率で行われている薬剤耐性の調査は世界的にもあまり例がなく、欧米の研究者仲間から高い評価をいただいています。解析したデータは全て公的データベースに登録されており。誰でも利用できるようになっています。
―調査から得られるデータにはどのような意味がありますか?
この調査による国内におけるHIV/エイズの感染動向の把握は大変に貴重で意義深いものだと思います。新規感染者における薬剤耐性の把握は適切な治療薬の選択に欠かせないだけでなく、遺伝子型や、感染経路なども把握できるので、このような疫学的データの蓄積は現状の理解だけでなく今後の感染症対策にも大きく貢献すると思います。
◆ 杉浦 亙(すぎうら・わたる)氏
平成4年 浜松医科大学大学院医学系研究科修了(医学博士)
平成4年 国立静岡病院内科医長(呼吸器内科)
平成6年 米国 NIH/NIAID 客員研究員
平成8年 国立感染症研究所エイズ研究センター、第 2 研究グループ長
平成20年 国立病院機構名古屋医療センター、臨床研究センター 部長
平成21年 名古屋大学大学院医学系研究科免疫不全統御学講座 客員教授
平成25年 第10回日本エイズ学会学術賞(シミック賞)を受賞
平成27年 グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部メディカルアフェアーズ部門上席部長
平成30年 ViiV Healthcare Asian- Pacific Medical Director
令和元年 ビオメリュー・ジャパン メディカルアフェアーズ本部長
令和 2年 国立国際医療研究センター 臨床研究センター長
令和4年 日本エイズ学会 理事長
【受賞】
平成25年 第10回日本エイズ学会学術賞(シミック賞)
編集後記
約20年前、HIV/エイズは社会的な偏見や誤解も根強く存在していました。「クイーン」のフレディ・マーキュリー氏がHIV感染を背景にニューモシスチス肺炎を発症し亡くなったことなどが影響しているとも考えられます。現在は、医学的理解と治療法が飛躍的に進展しています。HIV検査も保健所等で匿名かつ無料で受けられる体制が整えられています。またHIV陽性であっても早期に治療を開始することで、健康な人とほぼ変わらない日常生活を送ることが可能になっています。
まずは感染予防を正しく行い、もし感染の可能性を感じたら、速やかに検査を受けることが大事です。早期の対応が、身体的・精神的な健康を守る第一歩となります。本記事が、HIV/エイズに対する理解を深め、より健やかな日常への一助となれば幸いです。